「城塞」中巻は、上巻には影も形も表さなかった真田昌幸・幸村親子の登場から始まる。
大河ドラマでも「真田丸」が取り上げられているが、やはり大坂の陣のスターは真田幸村であろう。
巻中、真田幸村をドン・キホーテになぞらえる文学史的記述があり、大いに興味をそそられたが、まさに言い得たりとの感を持った。
司馬氏の言うとおり、中世において日本はドン・キホーテの様な一時代の終わりを告げる文学を持たなかったが、
真田幸村という実人物をして時代の終わりを告げさせるところが面白いと思った。まさに、快男児といった風である。
中巻は、真田幸村の九度山脱出に始まり、大坂に参集する武将の列伝が語られ、
大坂冬の陣の経過が東西の人間模様と共に語られるものとなっている。
最後は大坂冬の陣の講和が成り、世に有名な大阪城の堀が埋められ、裸城になる場面で終わっている。
僕は豊臣秀吉贔屓で昔から徳川家康は好きではなかったが、城塞を読むとその悪辣非道ぶりにあきれるばかりである。
大坂冬の陣を眺めていると、やはり誰もが思うであろう、真田幸村が大坂方の総大将になり指揮を取らせていたら、
と言った「たられば」が浮かんできてしまう。
「城塞」を含む大阪冬の陣・夏の陣の物語は、大会社の倒産物語に似て示唆に富む。
真田幸村や後藤又兵衛のような有能な営業部長クラスがいても、秀頼社長がお飾りであったり、淀君のようなヒステリーがいたり、
大野修理治長のように危機意識は持っていてもトップの意見を忖度ばかりしているような専務取締役がいては
どうにもならない事が再認識できる。
幹部クラスが無能である分、現場の有能さ清々しさが引き立つ構成となっており、
それ故に大坂方没落のやるせなさが身にしみてくるのである。
中巻で驚くのは、やはり凡庸だと思っていた豊臣秀頼が以外にも有能ぶりを示す一端が垣間見える部分である。
大阪城の奥の奥で育っていたら凡庸のままであったが、大坂の陣という未曽有の危機におよび、
今まで会う事も無かった後藤又兵衛、真田幸村といった人物に出会う事で才能が開花していく部分は清新の気をもたらす。
ここでもやはり、危ない会社の見分け方ではないが、社長が現場へ行く事の重要性、社長が現場の意見を聴く事の重要性を
学ばせてくれる。
組織がしっかりしていて、取締役等の社長の取りまきが現場の意見をよく聞き、経営判断に資する情報をトップにもたらせていれば、
社長自身が頻繁に現場に行く必要は無いであろう。
さて、次巻はついに大阪城落城、倒産の時を迎える。
倒産におよび社長、取締役、現場がどのような人間模様を見せるのか楽しみである。
司馬遼太郎 「城塞」(上・中・下巻)

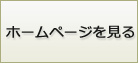
コメントする